各省庁へきこえない・きこえにくい人の社会参加に関わる要望を提出
2025年7月14日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。また、一部の省庁へは要望書を送付しました。
| 各省庁名・担当課 | 全日本ろうあ連盟出席者 |
|---|---|
| 警察庁(7月14日)交渉風景と提出した要望書へ 長官官房 人事課 会計課 企画課 総務課 生活安全局 生活安全企画課 交通局 運転免許課 |
副理事長 中西 久美子 事務局長 久松 三二 福祉労働委員長 大竹 浩司 情コミ委員長 吉野 幸代 国際委員長兼 情コミ副委員長 嶋本 恭規 |
| 内閣府(7月14日)交渉風景と提出した要望書へ 政策統括官(共生・共助担当)付 参事官(障害者施策担当) |
|
| 厚生労働省(7月14日)交渉風景と提出した要望書へ 職業安定局 障害者雇用対策課 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 障害保健福祉部 障害福祉課 総務課 |
|
| 文部科学省(7月14日)交渉風景と提出した要望書へ 初等中等教育局 特別支援教育課 総合教育政策局 教育人材政策課 大臣官房 会計課 国際統括官 ユネスコ協力官 |
副理事長 河原 雅浩 本部事務所長 山根 昭治 スポーツ委員長 太田 陽介 スポーツ事務局長 山田 尚人 教育文化委員長 堀米 泰晴 教育文化副委員長 櫻井 貴浩 福祉労働副委員長 小林 泉 |
| スポーツ庁(7月14日)交渉風景と提出した要望書へ 参事官(地域振興担当)付 参事官(国際担当)付 競技スポーツ課 健康スポーツ課 政策課 |
|
| 国土交通省(7月14日)交渉風景と提出した要望書へ 大臣官房 総務課 道路局 高速道路課 鉄道局 鉄道サービス政策室 都市鉄道政策課 物流・自動車局 旅客課 都市局 街路交通施設課 総合政策局 共生社会政策課 |
|
| 経済産業省(7月14日)交渉風景と提出した要望書へ 商務・サービスグループ 博覧会推進室 |
|
| 厚生労働省(9月10日)交渉風景と提出した要望書へ 社会援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 障害保健福祉部 障害福祉課 老健局 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 老人保健課 医政局 総務課 |
「福祉基本政策プロジェクトチーム」 ・全日本ろうあ連盟 ・全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会 ・全国ろう重複障害者施設連絡協議会 ・全国聴覚障害者情報提供施設協議会 ・全国手話通訳問題研究会 ・全国ろうあヘルパー連絡協議会 |
|
送付した要望書一覧: こども家庭庁: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 総務省: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 国税庁: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 法務省: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 外務省: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 金融庁: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 消費者庁: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 文化庁: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 消防庁: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について 経済産業省: きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について |
|
【 送付した要望書 】
連本第250217号
2025年7月29日
こども家庭庁長官
渡辺由美子様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.「聴覚障害児支援中核機能強化事業」を法制化し、すべての自治体を対象とした聴覚障害児支援事業を必須事業としてください。
<説明>
「聴覚障害児支援中核機能モデル事業」が「聴覚障害児支援中核機能強化事業」となってから、初めての年となる2024(令和6)年度の事業実施自治体数は23自治体です。この数字から見ても、全国どこでも等しく支援が受けられるという状況には至っていないことがわかります。
本事業は、きこえない・きこえにくい子どもとその保護者の将来に大きくかかわる、非常に重要な内容です。自治体の必須事業として、すべての自治体が本事業を実施できるよう、以下を含む聴覚障害児支援対策の法制化を要望します。
・すべての自治体を対象とした「聴覚障害児支援事業」の必須事業化
・聴覚障害児の「手話言語獲得」のための「手話言語獲得支援事業」の予算化
・保護者の「手話言語習得」に必要な支援の予算化
2.全国的な聴覚障害児支援のネットワークを立ち上げ、都道府県の「聴覚障害児支援中核機能強化事業」の実態の把握と情報の共有を図り、全国どこでも同じ支援や情報が得られる取り組みを図ってください。
<説明>
各自治体で実施されたモデル事業の報告書がホームページに掲載されていますが、他の自治体がこの報告書を参考に取り組むことはできても、自治体それぞれの考え方や受け止め方が異なるため、保護者や家族に提供した情報や支援の内容などの情報共有が十分に行われず、全国どこでも等しく支援が受けられるとはいえません。
年に一度、情報交換の機会を設けるほかにも、全国的な聴覚障害児支援中核機能を持つ機関を立ち上げるという考え方もできます。
この機関は、各自治体で実施されている事業の実態調査や情報の共有、各自治体からの相談窓口を請け負い、聴覚障害児支援のノウハウの開発や蓄積、展開を行う機能を持たせ、全国どこでも等しく支援が受けることができ、偏りのない情報が得られる仕組みづくりを図ってください。
3.聴覚障害児が児童発達支援センターや保育所等を利用する際は必ずきこえない・きこえにくい当事者のスタッフを配置すること、聴覚障害者情報提供施設またはろう協会との連携が取れる体制を構築してください。
<説明>
児童発達支援センターや保育所等の、きこえない子どもに接する職員がきこえないことについて充分に理解されていないために的確な支援を受けられないケースがあります。きこえない当事者のスタッフや聴覚障害者情報提供施設またはろう協会との連携をとり、問題を解決してください。
また、きこえに問題をかかえる子どもは聴力が比較的良くても、周囲の音や言葉が聞き取りにくいことに変わりはありません。言語発達の途上にある子どもにとっては、視覚的に見てわかるコミュニケーション支援が必要ですので、利用の等級制限の解除を求めます。
4.貴庁の障害者の施策に影響を及ぼす委員会には、必ずきこえない当事者を参画させてください。
<説明>
厚生労働省及びこども家庭庁に共通する課題として、きこえない委員が参画していない労働部会、介護保険部会、医療保険部会、こどもの居場所部会等は、きこえない人の実態やニーズが充分に把握されず、考慮されないことが往々にしてあります。
他にも、「当事者を対象に調査した」という報告書が出ても、実際にはきこえない人やきこえない人の課題が全く盛り込まれていないケースが散見されます。当事者が委員に入ること、また委員として参加しない場合には、充分なヒアリングを行うことを求めます。
5.旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下、補償法)に基づき全ての被害者に対する補償と優生思想の根絶に向けた恒久対策を進めてください。
<説明>
補償法に基づき、全被害者への速やかな謝罪と補償を実現すべく、①~③の施策を検討・実施をお願いします。
また、二度と同じ過ちを繰り返さないよう、優生思想及び障害者に対する偏見差別を根絶し、子を生み育てることを自ら決定でき、全ての個人が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、尊厳が尊重される社会を実現してください。
①相談窓口、相談体制の整備
国及び各都道府県における相談窓口を整備し、相談及び申請に際しての合理的配慮及び情報保障(手話言語を含む)を徹底することのみならず、被害者の負担の少ない場所での相談体制の構築、充実化を図ってください。また、情報保障等にかかる費用は全国共通の基準で対応するようにしてください。
②広報、周知等の徹底
すべての被害者に情報が行き届くよう、障害者手帳・自立支援医療受給者証の保有者へ周知文書の送付など、合理的配慮・情報保障を尽くした形での広報、周知、とりわけ、きこえない人にも分かるように視覚的で分かりやすい内容を、あらゆる手段、かつ継続的に実施してください。
③個別通知と被害者調査の実施
(1)個別通知(個別対応・アプローチ)の実施
所在が把握できた被害者に対する個別通知(個別対応・アプローチ)を全都道府県が積極的に実施するよう、国が適切な通知等を発出するとともに、必要十分な予算措置を講じてください。
(2)被害者の徹底的な調査の実施
国及び都道府県が保有する資料の調査のみならず、当連盟などの当事者団体、医療機関、福祉施設等が保有する資料についても徹底的な調査を実施し、被害者を把握すべく、国が適切な通知等を発出するとともに、必要十分な予算措置を講じてください。
≪各省共通項目≫
6.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
7.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
8.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
9.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
10.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250218号
2025年8月1日
総務大臣
村上 誠一郎 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.きこえない・きこえにくい者等の参政権の保障のために、以下を要望します。
(1)政見放送への手話通訳、字幕の挿入を義務づけてください。
<説明>
現在、国政選挙・都道府県知事選挙の政見放送には、すべてに手話通訳・字幕の付与が実現されておらず、義務付けも行われていません。経歴放送には字幕もなく、音声放送のみでは候補者の経歴を知ることができません。きこえない・きこえにくい者等がきこえる人と同等に選挙に関する情報を得て、その選挙権を行使できるよう、政見放送への手話通訳、字幕付与の義務付けができるよう、改正をしてください。
(2)候補者が行う街頭演説に手話通訳や要約筆記等をつけることについて、制限を撤廃してください。
<説明>
現在、「選挙運動に従事する者」の中の「専ら手話通訳のために使用する者」として報酬を支払うことができることになっています。
しかしながら、手話通訳者は自らの意見を述べたり、候補者の応援をする「選挙運動に従事する者」ではなく、公正中立な立場で情報保障を担う者です。「選挙運動に従事する者」としてではなく、『手話通訳者』として報酬が支払えるようにしてください。
また、これまで「選挙運動に従事する者」であることを理由に、公務員である手話通訳士は選挙に関する手話通訳を行うことができませんでしたが、その見直しを図り、公務員であっても選挙に関する手話通訳を行えるようにしてください。
併せて、文字による情報保障として、字幕や要約筆記等をスクリーン等に投影する方法は認められていますが、屋外では投影することが禁止されています。情報アクセシビリティの観点から必要な改正をしてください。
(3)2017~2025年度、貴省予算で実施しています「政見放送手話通訳士研修会」(地方研修会)を2026年度以降も継続して行えますよう、引き続き予算化をしてください。また選挙関連の手話の確定費用も予算化をお願いします。
<説明>
政見放送の手話通訳を担う者は、「政見放送及び経歴放送実施規定」により手話通訳士となっています。すべての政見放送において手話通訳挿入が実現した後も、政見放送を担える手話通訳士を継続して増やす必要があります。更に政見放送では社会情勢や時事問題等、専門的かつ新しい用語が使われ、手話通訳士も継続して通訳技術を磨く必要があることから、研修の履修更新制を設けており、今後も新規手話通訳士合格者や関係法令等の改正の理解及び政見放送内容に関わる新しい手話の習得のために「政見放送従事者研修会」が必須となります。
2026年度以降も地方研修会を継続して行えるよう、予算化してください。また、新しい手話の確定は、厚労省の委託を受け標準手話の普及確定を行っている(社福)全国手話研修センターに依頼しています。しかしながら、選挙関連の新しい手話の用語確定は厚労省の委託対象外となっていますので、その費用も予算化をしてください。
2.首相官邸の記者会見等における手話通訳について、テレビ放送でも手話通訳者が映るよう放送事業者に通知してください。
<説明>
2011年3月11日の東日本大震災の発生後、首相官邸で行われる記者会見には手話通訳が付くようになりました。また、今般、重要な記者会見においては、多くのテレビ局がライブ放送で画面に手話通訳者の映像を組み入れて放送しており、従来に比べ、リアルタイムに情報を得ることができるようになりました。
放送事業者が、その手話通訳の映像をテレビ放送に乗せることで、きこえない・きこえにくいテレビ視聴者が、きこえるテレビ視聴者と同じタイミングで発言内容を知ることができるようになります。それこそが「アクセシビリティが保障された環境の整備の促進」です。
内閣府では、会見の際に話者の隣に手話通訳を配置されていますが、手話通訳を映すかどうか、また映す場合の大きさや、ニュース等での紹介時に通訳が映るかどうかは各放送局の判断と対応に任されています。しかしながら、2021年に改正された障害者差別解消法で、2024年4月からは民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されたことを踏まえ、きこえる人ときこえない・きこえにくい者の情報格差の出ないよう、各放送局の対応を注視するとともに、どの放送局でもユニバーサルな放送が行われるように通知をしてください。
3.放送以外のオンデマンド視聴やNetflixなどの配信プラットフォーム等について、情報バリアフリー支援事業の取り組みを強く推し進め、動画配信のアクセシビリティの向上を要望します。
<説明>
昨年、動画配信を行う事業者などに字幕・手話言語付与の目標を課すことは困難であること、また障害がある方などのICTの利便性向上を目的とした「通信放送分野における情報バリアフリー促進支援事業」に取り組んでいることをご回答いただきました。
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第13条では、「国及び地方公共団体は、(中略)放送、文化芸術、スポーツ、レクリエーション(中略)その他の障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野において、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするため、障害者とその他の意思疎通の支援を行う者の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。」と明記されています。
国として、多くの企業等が支援を受けられるよう強く事業を推し進め、動画配信のアクセシビリティの向上に取り組んでください。
4.DVD制作事業者に対して、放送事業者の番組を収録したすべてのDVDに字幕を付与する支援を講じてください。
<説明>
昨年、字幕利用については、放送事業者自らの取り組みにより行われることを期待しているとご回答いただきました。
しかし、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第13条に規定されているように、国としてDVDに日本語字幕を付与するための施策を講じるべきだと考えます。
実際に、多くのきこえない・きこえにくい者からの日本語字幕の付与に関する声が絶えません。きこえない・きこえにくい者もDVDを楽しむことができるよう、DVD制作事業者に対して、日本語字幕の付与に関する支援を講じてください。
5.地上波放送における災害時の緊急放送を、著作権法第37条の2に定められている指定事業者による異時再送信が実施できるようにしてください。
<説明>
災害時の緊急情報を異時再送信できる事業者の指定は貴省にて行われていますが、指定事業者はNHKや民放等に限られており、著作権第37条の2に指定されている事業者は含まれていません。
異時再送信には時間差があるため、災害発生時の情報としては即時性に欠けるという課題がありますが、現在の指定放送事業者による情報提供は音声言語が中心となっています。字幕や手話言語を付与した異時再送信は非常に限定的であり、きこえない・きこえにくい者が災害時にアクセスできる情報量は、きこえる人と比較して少ない状況です。著作権第37条の2で指定される事業者によって手話言語が付与された災害時の情報を、きこえない・きこえにくい者が安心してアクセスできるよう要望します。
≪各省共通項目≫
6.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
7.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
8.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
9.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
10.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250219号
2025年7月29日
国税庁長官
江島 一彦 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
2.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
3.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等(税務署等)における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等(税務署等)における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
4.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
5.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250220号
2025年7月29日
法務大臣
鈴木 馨祐 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.裁判所等の司法への手話言語によるアクセスを保障してください。
<説明>
現在、民事裁判での手話言語通訳派遣費用は「訴訟費用」として扱われ、基本的に敗訴した側が負担することになっています。そのため、手話言語通訳を必要とする者が訴訟を行うことを躊躇する状況が生じています。さらに、裁判の傍聴においても手話言語通訳の手配環境が整っておらず、傍聴しづらいのが現状です。
2024(令和6)年7月3日の優生保護法に関する国家賠償請求訴訟の最高裁大法廷判決では、傍聴者向けの手話言語通訳が裁判所の負担で手配され、判決文もモニターに投影されました。これは評価すべき対応です。
しかし、最高裁はその後「訴訟事件における聴覚障害のある傍聴人に対する手話言語通訳者の手配等について(事務連絡)」を各地の地裁・高裁に通達しましたが、この通達後に手話言語通訳の申請をしても認められない事例が発生しています。
日本国憲法第32条が保障する「裁判を受ける権利」を実現するためには、法廷内外を問わず、手話言語通訳者の派遣が不可欠です。きこえない・きこえにくい者の権利救済と人権擁護の観点からも、司法へのアクセスの確保を目的とする手話言語通訳を含めた情報アクセシビリティに関する費用を予算化してください。またこれらの整備に法改正が必要であればそれも含め対応をしてください。
2.国内の刑務所、少年刑務所及び拘置所並びに少年院、少年鑑別所等でのきこえない・きこえにくい者への情報・コミュニケーション保障の実態を教えてください。あわせて各刑務所へ「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に沿った合理的配慮の提供について周知してください。
<説明>
現在、日本国内においてきこえない・きこえにくい者が刑務所に入った場合、刑務官等からの合図や発言等に対して、きこえないことに伴う配慮がなされているか、お教えください。これまで、他の囚人の動きをみて自分の行動を決めた、何を言っているのかわからないまま時間を過ごしたという話も聞いています。情報保障がなければ、更正教育の意味をなさないまま、服役していたことになります。
1995(平成7)年に刑法40条「瘖唖者ノ行為ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減軽ス」が削除されてから約20年です。現在の刑務所、少年刑務所及び拘置所並びに少年院、少年鑑別所、婦人補導院等においける、きこえない・きこえにくい者への対応実績をご教示ください。
前回(9月3日)の説明では、書面によるやり取りや周知がほとんどで、手話言語が必要な受刑者は、情報から取り残されていないか懸念しています。手話言語による情報発信や刑務官等が手話言語を覚え対応できるよう職員の手話研修の実施等、環境の構築をお願いします。
あわせて、法務省の「法務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」では、対象者が望むコミュニケーション手段での合理的配慮が求められることについて、刑務所、少年刑務所及び拘置所並びに少年院、少年鑑別所等に周知をしてください。
≪各省共通項目≫
3.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
4.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話言語通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話言語通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話言語通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話言語通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話言語通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話言語通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話言語通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
5.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
6.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話言語通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話言語通訳等の配置がありますが、手話言語通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話言語通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話言語通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話言語通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話言語通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
7.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250221号
2025年7月29日
外務大臣
岩屋 毅 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.東京2025デフリンピック開催にあたり、外国のきこえない・きこえにくい者への情報保障・情報アクセシビリティの確保を積極的に行ってください。
<説明>
東京2025デフリンピックが今年11月に開催されるにあたり、各国の選手団等約6,000人のきこえない・きこえにくい者が来日します。空港や公共交通機関における案内、訪日外国人向けの動画等に国際手話通訳を付与するなど、外国のきこえない・きこえにくい者への情報保障・情報アクセシビリティの確保を積極的に行ってください。
また、外国のきこえない・きこえにくい者が訪日中にトラブルに遭った際には、駐日外国公館とも連携して情報保障を行っていただくよう、支援をお願いします。
あわせて、貴省および在外公館、駐日外国公館にて、東京2025デフリンピック啓発ポスターやデフリンピック代表選手応援横断幕などを掲げ、きこえない・きこえにくい者へ国境を越えた支援・応援ができるよう、貴省から呼びかけをお願いします。
2.国際協力分野に、きこえない・きこえにくい当事者の視点・声を取り入れるとともに、きこえない・きこえにくい当事者が参画できるよう、日本手話言語による情報発信を行うとともに、情報保障・情報アクセシビリティの確保を行ってください。
<説明>
SDGsの「誰一人取り残さない」社会を実現するためには、国内の取り組みに留まらず、発展途上国への支援が不可欠です。JICAを含め国際協力のあらゆる分野において、きこえない・きこえにくい者の視点・声を取り入れた事業展開が必要です。そのため、きこえない・きこえにくい者自身が国際協力分野に参画できるよう、日本手話言語による情報発信を行うとともに、情報保障・情報アクセシビリティの確保を行ってください。
3.障害者権利委員会からの総括所見を実現していくために当連盟と貴省において、定期的な対話を求めます。
<説明>
2022年9月に障害者権利委員会からの総括所見が出ました。総括所見では、第21条において、「46.(c)国として、日本手話が公用語であることを法律で認めること、あらゆる活動分野において手話を利用及び使用する機会を促進すること、有資格の手話通訳者の研修及び利用が可能であることを確保すること。」と勧告されています。この勧告を実現していくために、具体的な手段や方法、貴省が果たしうる役割のほか、ニーズが高まりつつある国際手話の制度整備も含めて、引き続き貴省と当連盟にて定期的に対話をしていくことを求めます。
4.障害者権利委員会 田門浩委員の活動において、手話言語による情報保障の十分な支援を引き続き求めます。
<説明>
2024年の障害者権利委員会にて、きこえない当事者である田門浩氏が委員にトップ当選しました。田門委員の情報保障にかかる側面支援に感謝します。
田門委員が障害者権利委員として活躍するためには、手話言語等による手厚い情報保障の継続が必要です。他方、国連においては、予算上の理由から、きこえない当事者の情報アクセシビリティに大きな課題が生じています。国連に対し、情報保障のための使途を特定した任意拠出金の拠出を検討してください。
また、世界情勢や国連の予算にかかる課題から、国連の組織統合や縮小により、障害者権利条約の効果的な実施・促進に懸念が持たれます。「アジア太平洋障害者の十年」ワーキンググループ等、関連情報を当連盟へ共有いただくとともに、アジア地域において障害者権利条約が促進されるよう日本政府から各国・各機関へ働きかけをお願いします。
5.国際会議における政府回答に日本手話言語を付けてください。
<説明>
2022年8月の日本政府と障害者権利委員会との建設的対話では、英語字幕及び国際手話通訳が付いていましたが、手話言語を公用語としている政府ではその国の手話言語通訳者を同行し、政府回答に手話言語通訳を付けていました。
そこで、日本政府におきましても、障害者権利委員会を含む国際会議において日本手話言語通訳を付けていただくよう要望します。
6.国連が定めた「手話言語の国際デー」においてライトアップを行い、「手話は言語」であることを積極的に発信してください。
<説明>
国連で定められた毎年9月23日の手話言語の国際デーにおいて、2022年より世界ろう連盟主導で、国連をはじめ世界各地でブルーライトアップを行っています。
つきましては、貴省におかれましてもブルーライトアップを行い、「手話は言語」であることを国民に積極的に発信してください。
(厚生労働省では9月21日の「世界アルツハイマーデー」で、オレンジ色のライトアップを実施しています。)
また、2025年9月23日に当連盟が主催する手話言語の国際デー啓発イベントに、外務大臣の出席をお願いします。
7.貴省管轄の在外公館及び国内の部署における合理的配慮の実例や実績を公開してください。
<説明>
2023年に貴省から在外公館へ、入り口のわかりやすい場所に「筆談マーク」を掲示するよう指示を出していただいた結果、この指示を受けて実際に対応した在外公館数及び、具体的な実例や実績を好事例として公開してくださるようお願いいたします。東京2025デフリンピックにおいて、海外のきこえない・きこえにくい者に向けて日本の取り組みを発信する好機と考えています。
また、貴省及び在外公館において、IT機器を通して手話言語オペレーターによる手話言語通訳を受けることができる「遠隔手話サービス」を導入したうえで「手話マーク」も掲示してください。
●手話マーク・筆談マークについて(URL)
https://www.jfd.or.jp/2016/12/01/pid15854

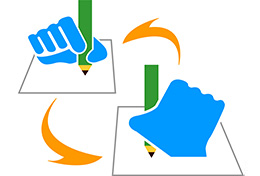
8.国連が推進している障害者権利条約と持続可能な開発目標(SDGs)の内容を日本手話言語で発信してください。
<説明>
貴省が発信している一部動画の文字化や字幕挿入の工夫に感謝します。
しかしながら、きこえない・きこえにくい者は日本語の文書を読むのが苦手な人もいます。
障害者権利条約の「手話は言語である」ことや、SDGsの「誰一人取り残さない」精神に鑑み、障害者権利条約とSDGsの内容を日本手話言語で周知してください。
また、外務省動画チャンネル等、貴省が発信している外務大臣会見をはじめとする動画全般に「日本手話言語」を入れてください。貴省からJICA、在日大使館、国連広報センター等の関係者へ手話言語の利用および使用について、喚起してください。
9.障害者権利条約を含む国際条約の「Sign Language」の和訳を「手話言語」にしてください。
<説明>
日本では言語としての「手話」と言語を表出する手段としての「手話」を混同して使い続けています。障害者権利条約について国民により正確に伝えるためにも、障害者権利条約第2条のSigned LanguageとSign Languageを「手話による言語」と「手話言語」と使い分けることが必要です。「手話は言語である」ことを日本政府として明確に示すためにも、当連盟より2019年12月17日付で貴省に要望したとおり、国際条約に記載されている「Sign Language」を手話言語と和訳し、貴省ホームページなどで公開してください。
≪各省共通項目≫
10.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
11.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話言語通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話言語通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話言語通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話言語通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話言語通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話言語通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話言語通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
12.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
13.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話言語通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話言語通訳等の配置がありますが、手話言語通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話言語通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話言語通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話言語通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話言語通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
14.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250222号
2025年7月29日
金融庁長官
伊藤 豊 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.きこえない者の情報アクセス、コミュニケーション保障の観点から、金融機関への問い合わせ先に、電話番号だけでなくFAX 番号もしくはEメールアドレス掲載の義務化を講じてください。
<説明>
金融庁の広報誌やパンフレット、ホームページ等は率先してFAX番号もしくはEメールアドレスを掲載し、金融機関等に対しても同様の対応をするように周知徹底をお願いします。また、キャッシュカードの裏面は電話番号だけになっているので、FAX番号もしくはメールアドレス掲載してください。
2.電話リレーサービスを利用した「本人確認」が有効であることを、金融機関等への周知を進めてください。また、ホームページ等の問合せ・受付について、電話窓口だけではなく、FAX、メール、チャット等の多様化をお願いしてきましたが、手話言語使用者のために「手話対応窓口」の拡大指導をしてください。
<説明>
電話リレーサービスによる「本人確認」も電話と同等の内容で行えるよう、周知をお願いします。また、アクセシビリティの向上の観点から電話窓口だけでなく手話対応窓口を含めた多様な方法で窓口対応ができるよう周知・指導をお願いします。
3.金融機関へ手話言語通訳者を介して電話をしている場合でも、きこえない本人が電話をしていることの理解と周知をしてください。
<説明>
上記2とは逆に、電話リレーサービスについて周知されている金融機関等では、従来のように手話言語通訳者等を介して電話をした場合、電話リレーサービスではないという理由で本人確認ができないと拒否される事例があります。スマホやタブレットを持っていないために電話リレーサービスを利用できないきこえない人もいることを理解いただき、周知徹底をお願いします。
障がい者団体と金融機関団体との意見交換会に要望を出しましたが、改善がみられませんでしたので、更なる周知をしてください。
4.銀行のアプリを使ったインターネットでの振り込みや住所変更などの手続き(インターネットバンキング)を利用する際に、ワンタイムパスワードを有効にするために、電話による確認を求められることがあります。きこえない・きこえにくい者でも利用しやすいよう、電話の音声に代わる方法を導入するよう、金融機関等へ働きかけてください。
5.ATMを利用しトラブルが生じた際には、備付の緊急電話以外の方法で問い合わせができるようにしてください。
<説明>
ATMのみの無人店舗や有人店舗でも早朝・夜間や休日など営業時間外でトラブルが生じた際には、備付の緊急電話で問い合わせることになりますが、きこえない者は電話での通話ができません。周囲に人がいない場合は問い合わせすらできません。
緊急電話の受話器を持ち上げ応答がない場合には、金融機関の職員や警備会社が駆けつけて対応すると聞いていますが、通じているのか、対応してくれるまでにどのくらいの時間を待てばよいのか分かりません。電話に代わる方法として、タッチパネルによる文字送信等を導入するなど、情報アクセシビリティの基礎的な環境の整備を関係の金融機関等に働きかけてください。
また今後、新しくATMを開発される際には、きこえない者からヒアリングを行い開発するよう指導してください。
6.金融機関等の窓口に手話言語ができる職員の配置や遠隔手話サービスを導入し、窓口には手話マーク・筆談マークの表示をしてください。
<説明>
遠隔手話サービスとは、お店や病院、行政機関の窓口などで、手話で対応が必要な時に手話が出来る店員・職員がいない場合、タブレットやテレビ電話で、手話言語通訳を呼び出して応対するサービスのことです。そのサービスの導入と下記のマークの設置を促進してください。
全日本ろうあ連盟で作成したマーク

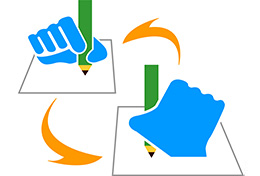
https://www.jfd.or.jp/2016/12/01/pid15854
≪各省共通項目≫
7.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
8.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話言語通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話言語通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話言語通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話言語通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話言語通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話言語通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話言語通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
9.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
10.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話言語通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話言語通訳等の配置がありますが、手話言語通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話言語通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話言語通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話言語通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話言語通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
11.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250223号
2025年7月29日
消費者庁長官
堀井 奈津子 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.事業者や法人等に2021年から公的インフラとなった電話リレーサービスの認知を拡げ、その通話が拒否されないよう周知いただくとともに、電話による「本人確認」と同等に電話リレーサービスや手話言語通訳による確認などでも「本人確認」ができるよう働きかけをしてください。
<説明>
電話リレーサービスの効果的かつ継続的な周知をお願いします。
また、電話リレーサービスの「本人確認」が認められないケースや、手話言語通訳を介して確認が行われる場合は電話リレーサービスではないという事由で、「確認できない」とされるトラブルが後を絶ちません。貴庁から改善の指導をしてください。
2.きこえない者の情報アクセス、コミュニケーション保障の観点から、貴庁はもちろんのこと、貴庁の出先機関や貴庁が管轄する食品等の問い合わせ先に、電話番号だけでなくFAX 番号もしくはEメールアドレス掲載するよう指導をしてください。
<説明>
消費者庁の広報誌やパンフレット、ホームページ等は率先してFAX番号もしくはEメールアドレスを掲載し、各地消費生活センター窓口等に対しても同様の対応をするように周知徹底をお願いします。また、食品等の問い合わせ先に電話番号だけになっていることが多いので、FAX番号もしくはメールアドレス掲載するよう指導をしてください。
≪各省共通項目≫
3.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
4.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話言語通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話言語通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話言語通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話言語通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話言語通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話言語通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話言語通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
5.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
6.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話言語通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話言語通訳等の配置がありますが、手話言語通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話言語通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話言語通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話言語通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話言語通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
7.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250224号
2025年7月29日
文化庁長官
都倉 俊一 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話 03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石 橋 大 吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.きこえない・きこえにくい者がきこえる人と同様の情報にアクセスできるよう、文化施設(博物館や美術館等)での展示や設備などにおいて、視覚的な情報アクセシビリティを拡充するよう全国の文化施設に働きかけてください。
<説明>
広島平和記念資料館や富岡製糸場等の文化施設での展示や設備などで、手話言語の動画を用意するといった視覚的な情報アクセシビリティの整備が進んでいますが、このような施設は全国的にまだまだ少ない状況です。
昨年、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を踏まえ、関連する施策を総合的かつ計画的に推進しているとのご回答をいただきました。基本計画で掲げられている目標の一つに「文化施設及び福祉施設等をはじめとした関係団体・機関等の連携等による、障害者が文化芸術に親しみ、参加する機会等の充実」があります。この目標を達成することができるよう、さらに国として全国的に視覚的な情報アクセシビリティを推し進めるよう、文化施設に働きかけてください。
また、文化施設の改修や新築する際には、実際に改修および建築が行われる前に、その地域の当事者団体の声を聞く機会を設け、施設内の情報アクセシビリティを含むバリアフリー化に反映するよう働きかけてください。
2.字幕が付与された焼き付け版作品の上映回数を増やすよう、全国興行同業組合連合会に働きかけてください。
<説明>
昨年、民間企業等においても、障害者への鑑賞サポートやDVDを含む映画作品等のバリアフリー化等の取組が行われていると承知しているとのご回答をいただきました。
「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」では、施策の一つとして「鑑賞の機会の拡大」が掲げられています。字幕付き上映の頻度や時間帯の設定が上映館の裁量によることは承知していますが、「鑑賞の機会の拡大」に取り組むためには、国として上映館等に働きかけをしてください。
≪各省共通項目≫
3.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
4.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話言語通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話言語通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話言語通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話言語通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話言語通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話言語通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話言語通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
5.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
6.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話言語通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話言語通訳等の配置がありますが、手話言語通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話言語通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話言語通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話言語通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話言語通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
7.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250225号
2025年7月29日
消防庁長官
大沢 博 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.緊急自動車の状態が見て分かる警光灯について、全国の消防本部や地方公共団体へ周知してください。
<説明>
緊急自動車の警光灯が、緊急かそれ以外の走行か視覚的に判断できるよう要望しました。2024年度から一部の回転灯製造会社で出荷が開始され、福島県郡山市の消防局で、全国で初めて新型警光灯の導入がなされました。
https://www.minpo.jp/news/moredetail/20250219122609
きこえない・きこえにくい者が安心していられるよう、緊急自動車の状態が見て分かる警光灯の導入拡大にむけて、予算措置を行い、全国の消防本部や地方公共団体へ一刻も早い導入を促してください。
≪各省共通項目≫
2.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
3.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話言語通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話言語通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話言語通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話言語通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話言語通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話言語通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話言語通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
4.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
5.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話言語通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話言語通訳等の配置がありますが、手話言語通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話言語通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話言語通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話言語通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話言語通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
6.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上
連本第250226号
2025年7月29日
経済産業大臣
武藤 容治 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax.03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の施行や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が施行しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.2021 年から公的インフラとしてスタートした電話リレーサービスについて、引き続き周知を進めてください。また、電話リレーサービスを利用した場合に「本人確認」に支障が出ないよう周知をしてください。
<説明>
2021(令和3)年4月20日付、総務省総合通信基盤局長から金融庁監督局長及び経済産業省商務・サービス審議官宛に、「各企業等に対し、電話リレーサービスを介した「本人確認」が有効である」ということ周知を依頼する文書が出されています。しかしながら十分に周知されているとは言えない状態です。電話リレーサービスの利用に支障が出ないよう、信販会社等をはじめとする様々な事業者への周知を進めてください。
2.クレジットカード会社へ手話言語通訳者を介して電話をしている場合でも、きこえない本人が電話をしているという理解とその周知拡大をしてください。
<説明>
電話リレーサービスについて周知されているクレジットカード会社では、従来のように手話言語通訳者等を介して電話をした場合、電話リレーサービスではないという理由で拒否される例があります。スマホやタブレットを持っていないために、電話リレーサービスを利用できないきこえない人もいることを理解いただけるよう、貴省からも働きかけをしてください。
また、手話言語通訳者等を介しても、金融機関と連携したクレジットカードでは、金融機関へ回され電話リレーサービスで対応するようにと案内されています。このような一連の手続きには30分以上もの時間がかかるため、早急に改善するよう働きかけをしてください。
3.店舗等のレジ(受付)における配慮について、「コミュニケーション支援ボード」を常置すること、またきこえない者への接遇研修を行うよう、企業や事業者に周知してください。
<説明>
スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストア等、身近な店舗のレジや受付において、コミュニケーション支援ボードの常置のお陰で利用しやすくなりつつあります。しかしながら店員の問いかけに気がつかなかったり、話しの内容が理解できず誤解が生じる等、困る事例が多くあります。また、マスク着用によって口の動きや表情が見えない場合や、日本語が堪能ではない外国人店員の場合など、更にコミュニケーションが困難となっています。きこえない者が安心して買い物ができるよう、使いやすい「コミュニケーション支援ボード」の常置や、きこえない・きこえにくい者への対応方法等を学習できるよう、企業や事業者に周知してください。また合理的配慮がされている企業を好事例としてHP等で公開し、きこえない・きこえにくい者が使えるようにしてください。
4.きこえない・きこえにくい者が学びやすい環境を整えている学校・講座等の好事例を集め、HPなどで公開してください。
<説明>
近年、貴省主導でのリスキリング(新たな業務や職種で必要となるスキルや知識を習得すること)が広まっていますが、きこえない・きこえにくい者たちは、就職のために何らかの資格を取りたいと思っても、情報保障の問題で受講申込をあきらめるケースが多くあります。
きこえない・きこえにくい者でも学べるような配慮のある学校や講座の情報を収集し、貴省HPなどで好事例として閲覧できるようにしていただきたい。
5.2025 年日本国際博覧会において、情報アクセシビリティおよびコミュニケーションを保障する人材育成のための費用と開催中に手話通訳の情報保障が提供されるよう費用を予算化してください。
<説明>
2025年の大阪万博の基本計画には、「バリアフリー・ユニバーサルデザインを考慮するとともに、先端技術を用いることにより、国・地域、文化、人種、性別、世代、障がいの有無等に関わらず、大阪・関西万博を訪れる世界中の人々が利用しやすいユニバーサルデザインの実現を目指す」とあります。また、サービス提供体制として「来場者へ高品質のサービスを提供するため、十分な人員を確保し、多言語や手話言語対応等の適切な研修を実施すると同時にICTによる運営従事者サポートツールを活用できる体制の構築を図る」とも記されています。昨年「すべての来場者にとって、より利用しやすい博覧会会場の実現に向けて検討を進めています。」と回答いただきましたが、きこえない者への情報保障についてどのような対応を検討されているのか進捗状況をご教示ください。
折しも障害者差別解消法が改正され、2024年4月より民間事業者も含め、合理的配慮の提供が義務化となりました。新たな国際博覧会のモデルとしてアクセシビリティ環境整備にかかる予算を確保してください。
≪各省共通項目≫
6.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
7.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話言語通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話言語通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することは、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業にも含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話言語通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話言語通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話言語通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。
きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。
利用者から手話言語通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話言語通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省関係の出先機関を含め、周知徹底ください。
8.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
9.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話言語通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話言語通訳等の配置がありますが、手話言語通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話言語通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話言語通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話言語通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話言語通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
10.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上


